オフィス移転を成功に導くレイアウト構築の完全ガイド

オフィス移転は企業の成長や働き方の変化を反映する、大きな節目となるイベントです。移転に伴う最適なレイアウト構築は、業務効率や社員のモチベーション向上に直結するため、慎重な計画と専門的な知識が欠かせません。 本記事では、オフィス移転とレイアウト計画の重要性から具体的なレイアウト手法、費用相場、事例紹介、業者選定のポイントに至るまで、オフィス移転を成功へ導くための完全ガイドを提供します。
- 目次
-
オフィス移転とレイアウト計画の重要性
オフィス移転にあたっては、全体像を把握しつつレイアウト計画を立案することが成功の鍵となります。その重要性と基本的な考え方を整理します。
オフィスの移転は単なる場所の変更ではなく、自社のブランド戦略や働き方を再定義するうえで大切なプロジェクトです。社員の意見を幅広くヒアリングし、コミュニケーションの改善や業務効率の向上といった具体的なゴールを設定することが不可欠です。加えて、移転後のレイアウトが企業イメージをどのように刷新し、組織全体のモチベーションアップにつながるかを考慮することで、より効果的なオフィスづくりが実現します。
オフィス移転前に押さえておくべきポイント
円滑な移転を進めるには、事前準備として明確な目的設定や現状分析、スケジュール作成が必要です。ここでは、移転前に知っておきたいポイントを述べます。
オフィス移転は関係部門が多岐にわたるため、早い段階からプロジェクトチームを結成して、役割分担とスケジュール管理を徹底することが重要です。加えて、移転計画中には旧オフィスの契約や新オフィスの条件確認といった法的手続きも伴うため、スムーズに手続きを行うための体制づくりが求められます。社員の作業環境が大きく変わる点にも配慮し、配置や設備の変更についてもできるだけ納得感のある情報共有を行いましょう。
移転の目的を明確にする
オフィス移転の背景には、増床やコスト削減、企業のブランディング強化など、さまざまな目的が存在します。まずはそれらの優先順位をはっきりと定義し、経営陣や関係部署との合意形成を図ることが大切です。目的を明確にすることで、家具選定からレイアウトデザインまで一貫した方向性を持って意思決定が進められます。
オフィスの現状把握と課題分析
現行オフィスにおける問題点を把握するためには、社員アンケートやワークショップの開催などで直接的な声を収集することが効果的です。業務フローのボトルネックやコミュニケーション不足など具体的な課題を抽出し、改善案とあわせて整理しておきましょう。現状分析の結果をレイアウト計画に反映することで、移転後のオフィスは従業員のモチベーションをさらに高める空間へと進化します。
移転スケジュールと体制づくり
オフィス移転は長期的なプロジェクトであり、引越しや内装工事、各種インフラの更新など多くの工程が含まれます。早めのスケジュール作成と、移転プロジェクトチーム内での明確な役割分担によって、想定外のトラブルや遅延を最小限に抑えることができます。特にIT関連の準備や通信設備の切り替えは時間がかかることが多いため、計画段階からしっかりと時間を確保しておきましょう。
契約内容と原状回復工事の確認
旧オフィスを退去する際には、契約時に定められた原状回復工事の範囲や費用負担を事前に確認する必要があります。現状回復の条件によっては、工事期間やコストに大きな影響が出るため、引越し時期や予算にも関わります。新オフィスの契約条件もあわせて精査し、入居後に予期せぬ追加費用が発生しないよう十分に注意して計画を進めましょう。
基本のオフィスレイアウトパターンと特徴
オフィスレイアウトにはさまざまなパターンがあり、それぞれにメリットとデメリットがあります。代表的なレイアウトと特徴を紹介します。
レイアウト選定を行う際には、組織の規模、業務内容、コミュニケーションの種類などを総合的に考慮することが欠かせません。たとえば対向型であれば活発なコミュニケーションを、ブース型であれば集中力の向上を目指すなど、それぞれの特性を踏まえて最適な形を選びましょう。複数のレイアウトを組み合わせたり、フリーアドレスを活用したりと柔軟な設計ができるのも、現代のオフィスデザインの特徴です。
対向型レイアウト
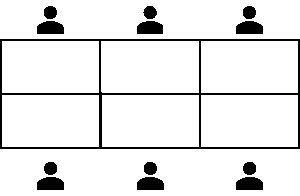
デスクを向かい合わせに配置する対向型は、向かいに座る同僚との会話や情報共有がしやすいというメリットがあります。一方で、正面に人がいるため落ち着かないと感じる社員もいるかもしれません。ユニット同士のレイアウトを工夫しながら、適度なパーティションなどでプライバシーを確保する方法が効果的です。
背面型レイアウト
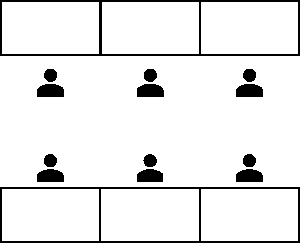
お互いの背中合わせにデスクを配置する背面型は、個々の集中力を保ちやすいのが魅力です。ただし、部署間のコミュニケーションが不足しやすい場合もあるので、共用スペースを活用して補う必要があります。背面型の採用を考える場合は、執務スペース以外のカジュアルミーティングエリアなどを併設することで、情報交換の機会を増やすようにしましょう。
同向型レイアウト
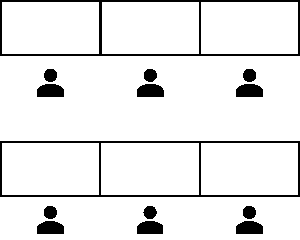
全員が同じ方向を向く同向型は、プレゼンやモニター共有に適した配列で、視認性を高めることができます。大人数が同時に情報を受け取りやすい一方で、周囲とのコミュニケーションが少なくなりがちです。導入する際には、適度に打ち合わせスペースを組み込むなどの工夫を並行して行うとよいでしょう。
フリーアドレス型レイアウト

固定席を設けずに自由にデスクを選べるフリーアドレス型は、多様な働き方やコミュニケーションを促進します。部署やチームの垣根を超えてアイデアを出し合える一方、この柔軟性がかえって落ち着きづらいと感じる社員もいる点には注意が必要です。明確なルールやゾーニングを設定し、目的別のゾーンを用意することでメリハリのある執務環境が実現します。
ブース型レイアウト

個別ブースを設けてプライバシーを確保しやすいのがブース型の特徴です。集中して作業したいエンジニアやコールセンター業務など、声を出す機会が多い職種に向いています。一方で、閉鎖的になりやすい分、チーム全体のコミュニケーションや情報共有の場を別途設ける配慮も重要です。
オフィスレイアウトに欠かせない3つの計画
レイアウト設計を行う上で、ゾーニング計画、動線計画、基準寸法計画を把握することが必要です。それぞれの概要を見ていきましょう。
これらの計画は単に机や椅子を並べるだけでなく、セキュリティレベルや組織連携の面からも考慮する点が多いのが特徴です。たとえばゾーニング計画で情報漏えいを防ぎつつ、動線計画で部署間の移動をスムーズにするなど、複数の視点から最適解を導く必要があります。社員が使いやすい寸法や通路幅を確保することで、安全面と快適性の両方を満たしたオフィスを実現しましょう。
出典:https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/bou_topic/kaguten/measures_office.html(オフィスの家具転対策 – 東京消防庁 参照)
ゾーニング計画
ゾーニング計画では、エントランスや受付エリア、会議室、執務スペースなどをセキュリティレベルや用途ごとに区分します。機密情報を扱うエリアへの立ち入り制限や、来客の動線管理などを明確にすることで、リスクを最小限に抑えられます。さらに、作業目的に合わせた区画編成を行うことで、社員の移動やコミュニケーションがより効率的になるでしょう。
動線計画
動線計画は、人や物の移動がスムーズに行えるよう、オフィスレイアウト全体の経路を設計することを指します。混雑を避けるために通路幅を広げたり、廊下や段差の位置を最適化したりするのが一般的です。部署間の往来を促進する配置であれば、コラボレーションの頻度も自然に高まり、情報共有が活発化します。
基準寸法計画
オフィス内を快適かつ安全に利用するためには、デスク間隔や通路幅などの基準寸法をしっかりと設定しておく必要があります。例えば、人がすれ違うのに必要な幅を最低限確保し、座席と座席の距離にも余裕を持たせることが推奨されます。こうした寸法計画が整備されることで、従業員はストレスなく作業を進められ、来訪者にも好印象を与えられるでしょう。
レイアウト設計の際に重視すべきポイント

快適に働けるオフィスを作るには、席数やデスク選定、インテリアなど多角的な視点が必要です。ここでは、特に押さえておきたいポイントをまとめました。
オフィスデザインは企業イメージを体現する重要な要素であると同時に、社員にとっては日々の作業環境となる場所です。ゆえに、デスクや家具の機能性はもちろん、空間デザインにおける演出や色彩の効果など視覚的な面も重視する必要があります。さらに、会議室やラウンジなど多目的スペースの配置は、業務内容やワークスタイルに合わせて柔軟に計画しましょう。
出典:https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/content/contents/001107615.pdf(職場における労働衛生基準が 変わりました 参照)
ワークスペースの広さと席数の確保
社員が快適に業務を行うためには、作業領域や机と机の間隔を充分に確保し、圧迫感を与えない空間設計が欠かせません。執務人数や業務形態に応じてレイアウトをカスタマイズし、業務効率を最大化できる席数と配置を検討しましょう。将来的な増員が見込まれる場合は、あらかじめ拡張性を考慮した計画を立てると柔軟な対応が可能です。
デスク・什器・オフィス家具の選定
デスクやチェアなどの什器は、業務効率や作業姿勢に直接影響を与えます。そのため、機能面だけでなくデザイン性やメンテナンス性も加味して選定することが肝要です。予算に余裕がない場合でも、リユース家具などコストを抑えられる方法を活用し、必要な性能と外観を両立させる工夫をすることが大切です。
おしゃれと機能性を両立するインテリア
企業のブランドやカルチャーを表現しつつ、社員が最適な環境で働けるよう配慮することがポイントです。照明や壁紙などのカラーコーディネートを統一すると、企業らしさを高めると同時に、オフィス全体に一体感をもたらします。観葉植物やアートワークを配置するなど、自然やアートの要素を取り入れることで、落ち着きと活気のバランスが整いやすくなります。
集中スペース・会議室・ラウンジの配置
社員が状況に応じて切り替えやすい空間づくりは、業務効率を大きく左右します。ミーティングスペースやラウンジを設置することで、気軽な会話やブレインストーミングがしやすくなり、部門を越えたアイデア創出にもつながります。一方で、個人作業に集中したい時には適度に区切られたブースやサイレントルームを用意し、メリハリのある働き方をサポートしましょう。
セキュリティと災害対策
オフィスの入退出管理や空調設備などは、社員の安全と安心を守るために欠かせない要素です。特にITセキュリティやサーバー室のアクセス制限等は、機密保持の観点からもしっかり整備する必要があります。さらに、防災グッズの設置や避難経路の確保など、緊急時の対応を想定したレイアウトの検討も怠らないようにしましょう。
オフィス移転の流れとチェックリスト

オフィス移転プロジェクトは多岐にわたるタスクで構成されます。重要なステップごとに準備を確認し、スムーズに移転するための流れを整理します。
各ステップごとにチームや担当者を明確化し、誰がいつ何をすべきかを見える化することが大切です。複数の業者や社内外の関係者が関わるため、情報伝達の滞りを防ぐ仕組みづくりも求められます。引越し後の定着フェーズにおいても、レイアウトの効果測定や微調整を行い、継続的に効率化を図りましょう。
コンセプト決定と理想のオフィス像づくり
まずは企業ビジョンやブランドに即したコンセプトを設定し、この移転によって実現したい理想のオフィス像を描きます。たとえば「コミュニケーション活性化」や「社員が働きやすい環境」など、具体的なキーワードを挙げることで初期段階から関係者全員の認識を合わせやすくなります。コンセプトが明確に定まると、この後のレイアウトやデザインの方向性もぶれにくくなるでしょう。
移転先オフィスの候補選定と内見
アクセスの良さや周辺環境、レイアウトの自由度を確認しつつ、複数の候補物件を比較検討します。内見の際は実際のスペース感を体感し、動線計画との相性や採光などの細部までチェックすることが大切です。候補を絞るだけでなく、物件の管理体制やセキュリティ面も合わせて把握しておくと後々のトラブルを防ぎやすくなります。
業者への見積もり依頼とスケジュール管理
契約前に複数の業者から見積もりを取り、費用とサービス内容を比較することで、コストパフォーマンスに優れた選択がしやすくなります。その際、レイアウト提案や施工期間、追加対応が可能かなども併せて確認すると、後々のスムーズな進行に役立ちます。十分に検討した上で契約を結び、スケジュールの詳細をすり合わせて各タスクを並行して進めましょう。
内装・設備・インフラ工事の打ち合わせ
新オフィスの内装や設備工事では、壁紙や床材、照明、インターネット回線など多くの要素を決定する必要があります。IT関連の配線やサーバー室の設置は、企業活動における基盤となるため特に入念な打ち合わせが欠かせません。全体デザインと機能性を両立させながら、故障やトラブルを最小化できるように配慮しましょう。
引越し準備と各種届出の手続き
引越し当日に向けて、荷物の梱包や家具の運搬順序、作業リストなどを細かく決めておくことがトラブル回避につながります。郵便・登記などの各種住所変更や取引先への連絡は、タイミングをずらせずに行う必要があるため注意が必要です。引越し後も電話番号やIT環境の切り替え、社員への周知などがスムーズに進むよう、最終的なチェックリストを活用して抜け漏れを防ぎましょう。
オフィス移転・レイアウトにかかる費用の目安

オフィス移転やレイアウト構築には、物件取得費や内装工事費などさまざまなコストが発生します。費用の目安を理解し、予算計画を立てましょう。
多様なコストがかかることを前提に、総額だけでなく各項目の内訳を把握しておくことが重要です。たとえば敷金・保証金や内装費用はもちろん、引越し作業や新たなオフィス家具の調達費まで含めて初期費用をリスト化します。想定以上に費用がかさむケースを考慮して、ある程度の予備予算を確保しておくと安心です。
主な費用項目の内訳
オフィス移転の主な費用項目には、物件取得費(敷金・礼金・仲介手数料)、内装工事費、ITインフラ費、引越し費用、オフィス家具・什器費用などが挙げられます。加えて、物件によっては管理費や共益費が大きく変動するため、契約書をよく確認しておきましょう。それぞれの項目を洗い出した上で、優先順位や必要度合いを検討することが予算管理の秘訣です。
コストを削減するための工夫
スケジュールの見直しや引越しシーズン外の作業日程を選ぶことで、人件費や物流コストを抑えられる場合があります。リユースやリサイクル家具を活用すれば、質を保ちながらもコストを大幅に削減することが可能です。また工事や引越し業者を一括で依頼できる体制を選ぶと、手間と費用を同時に減らせる場合も多いです。
予算に合った業者選びのポイント
提示される見積もりの明細を丁寧に比較検討し、基本料金以外の追加費用が発生しないかを確認することが大切です。複数社の見積もりを取り寄せて、デザイン力や対応範囲の広さ、スケジュール管理の実績なども総合的に考慮しましょう。自社のコンセプトや予算に合った柔軟な提案をしてくれる業者を選ぶことで、コストと品質を両立したオフィス移転を実現できます。
オフィス移転・レイアウト事例集
さまざまな規模や目的を持ったオフィス移転・レイアウト変更事例を紹介します。自社のオフィス計画に活かせるヒントを探ってみましょう。
他社の事例を参考にすることで、自社が取り組むべきオフィス移転やレイアウトの方向性を明確にできます。規模感や導入の目的が似ている事例はもちろん、全く異なる業種の事例にも学ぶべきポイントが潜んでいるものです。既存の課題に対する新しい解決策や、予想外の相乗効果を得られる場合もあるため、積極的に情報を取り入れましょう。
コミュニケーションを活性化するオフィス事例
社員同士が自然に会話を交わせるように執務エリアを配置し、部門の隔たりを感じにくいオフィスデザインを導入した事例です。コミュニケーションスペースの中央設置や、共有リソースを分散配置することで、人の動きを増やしながら部署間交流を活発化しました。結果として情報伝達のスピードが向上し、新しいビジネスアイデアが生まれるケースも増えたと報告されています。
コーヒーマシンを中心に会話が生まれる
休憩スペースにコーヒーマシンを設置し、部署を超えた社員が気軽に集まれる拠点とすることで、偶発的なコミュニケーションが増えた例があります。ちょっとした息抜きのつもりが、新しいアイデアのきっかけや他部署との連携強化につながることも少なくありません。こういった小さな工夫が、オフィス文化を活性化させる大きな要素となります。ダイオーズのオフィスカフェラウンジサービスを実際に導入した企業さまの事例はこちらです。
ABW導入で多様な働き方を実現した事例

アクティビティベースドワーキング(ABW)を導入し、プロジェクトルームやカフェスペース、静寂エリアなど、業務内容に合わせて社員が働く場所を選べるようにした事例です。自由度の高さから部門を越えたコラボレーションも盛んになり、新しいサービス開発や円滑なコミュニケーションが生まれました。一方で、初期導入時には使い方のガイドライン整備などのサポートが重要になります。
フリーアドレスを採用した柔軟なレイアウト事例

プロジェクトチームごとに必要なデスク数を柔軟に割り当てられるようにしたことで、迅速に体制変更ができるメリットを享受した事例です。部署や階層をまたいだ円滑な情報交換が可能になり、新入社員のオンボーディングもスムーズに行えるようになりました。ただし、席を固定しないことで個人の荷物管理などのルールを厳格化する必要があり、その運用体制の整備が求められます。
大規模オフィスにおける効率的な動線計画事例

フロア面積が広い場合は、ゾーニングと動線を綿密に計画しないと移動時間が無視できないレベルに達することがあります。ここでは部署やチームの関連性を踏まえ、配置ブロックの配置と通路幅を見直し、移動効率を高めました。結果として、非効率だった部門間の行き来が改善され、コラボレーションを生みやすい環境が整いました。
小規模オフィスでコストを抑えたレイアウト事例

限られたスペースしかない小規模オフィスでは、公私それぞれの用途を明確に分けるというより、空間を多目的に活用しながらレイアウトに工夫を凝らすことが成功の鍵です。共有エリアを打ち合わせにも使えるようにするなど、家具の配置や仕切りを工夫すればコストを最小限に抑えつつ作業効率を最大化できます。インテリアの選定でも多機能なデスクや椅子を導入し、狭さをカバーできるデザインを意識するとよいでしょう。
オフィス移転時に業者を選ぶ際のチェックポイント
オフィス移転やレイアウト構築の成否は、共に進める業者の品質に大きく左右されます。適切な業者選びのポイントを確認しましょう。
業者選びを誤ると、移転後のオフィスが計画と異なる仕上がりになったり、余計なコストが発生したりする可能性が高まります。そのため、実績やコミュニケーション能力、提案力などを総合的に見極めることが重要です。気になる点は初期の打ち合わせや見積もり段階でしっかり質問し、納得した上で契約を結ぶようにしましょう。
実績・担当領域の幅広さ
オフィス移転の経験が豊富な業者は、トラブルやイレギュラーにも柔軟に対応できるノウハウを持っています。デザインから施工まで一貫して対応できるかどうかを確認し、必要に応じてデザイナーやプランナーとの連携もチェックしておきましょう。幅広い業務領域を担える業者は、プロジェクト全体がスムーズに進められる可能性が高いといえます。
デザイン力とトータルサポート体制
オフィス空間そのものが企業のブランディングに影響を与えるため、魅力的なデザインを提案してくれる業者は重宝されます。さらに、コンセプト設定やアフターフォローまで含めてサポートしてもらえる体制があると、移転後の定着と改善もスムーズに進みます。興味のある業者が提示する過去の事例を参考に、デザインの幅やこだわりポイントを見極めましょう。
コミュニケーションと提案力の見極め
業者のヒアリング力は、理想のオフィスイメージを形にする上で非常に重要です。こちらの要望を的確に理解し、課題解決につながる具体的なプランを提示できるかを確認しましょう。コミュニケーションが活発に行われると、小さな変更点や追加要望にも柔軟に応じられ、結果としてより完成度の高いオフィスが実現します。
納期管理とアフターサポート
限られたスケジュールの中でも確実に納品してもらえるかどうかは、業者選定時の大切な評価ポイントです。特にオフィス移転の場合は、旧オフィスの退去期限など動かせない日程があるため、工程管理がしっかりしている業者を選ぶと安心です。移転後のレイアウト調整や追加施工など、アフターフォローの対応範囲も契約前に確認しましょう。
まとめ
オフィス移転は、新たなワークスタイルを実現し、社員の生産性と満足度を高める絶好のチャンスです。計画段階から十分な準備を行い、最適なレイアウトを構築することで、企業の成長を加速させる未来を築きましょう。
オフィス移転とレイアウト構築は、企業の運営戦略や社員のモチベーションを左右する大きなプロセスです。移転前の準備やスケジュール管理をしっかりと行い、実際のレイアウト選定では自社の目的や課題に沿った最適な形を模索しましょう。優れた計画と信頼できる業者のサポートを得ることで、コストを抑えながらも機能的で魅力的なオフィスを実現できます。







